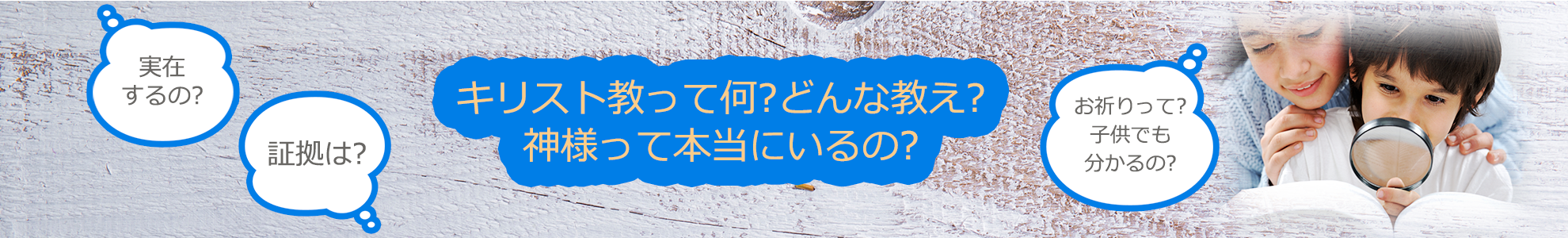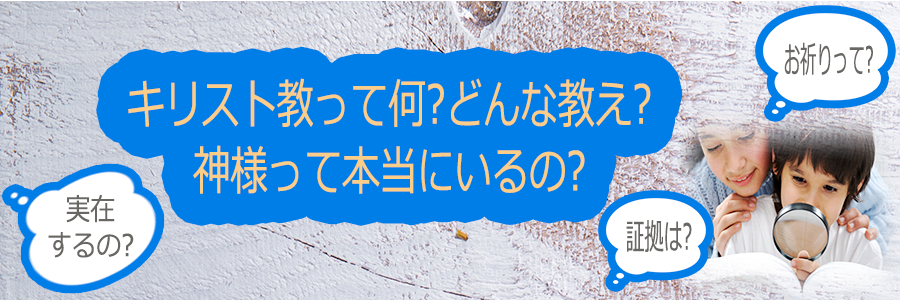
第17課 キリスト教の死後観
まえがき
この本の上巻は、世界の起源から新天新地の出現まで、神の側の「救いの経綸」についての叙述です。
これに対して下巻は、人間の側の問題、いいかえますと神の救いにあずかるための条件は何か。また救いを受け入れた者は、その後どのような生活を送ることになるのか、その規範についての学びということになります。
従って、本来なら、「神の救いの経綸」を信じ、受け入れた人に必要な学びであって、信仰がそこまでいっていないかたには、理解のむずかしい内容ということになろうかと思います。その意味で読んでも何が何やらわからないということになるかもしれません。しかし、自分には直接関係がないように思われても、また、たとい信じられないという人であっても、キリスト教とはどんな教えなのか、その概要を知っておくことは、決して無意味なことではないばかりか、本当はどなたにとっても必要なことではないかと思われます。
しかし、どうしても興味がもてないし理解もできないという方は、そこのところを飛ばして、はじめのほうの17課から20課まで(「死後の問題」と「救いの条件」について)は、どなたもぜひお読みになっていただきたいと思います。
それと、最後に収められている補遺(とくに2と3)だけは、欠かさずお目をとおしていただきたいと願っています。この部分は、天の神が直接みなさんがたに、個人的に語りかけておられるメッセージといってもよい内容のものですので、注意深く耳を傾け、そして、じっくりと咀嚼し、味読してくださるよう切望いたします。
はじめに
人間は神によって、しかも神にかたどって造られたと聖書に記されています。そのうえ人間は、最初条件つきながらも、神から永遠の命を与えられていたのです。その条件とは、神にたいする全的信頼と服従です。
だが、アダムとエバは、その条件を無視して神に従うことをしなかったために、死ぬべきものとなったのでした。その結果、アダムの子孫であるわれわれもまた、生まれながらにして死の運命を背負わされています。そういうわけで、この世に生を受けた者はすべて、いつかかならず死ななければならない定めにあるのです。
「一度だけ死ぬことと、死んだ後さばきを受けることとが人間に定まっている…」(ヘブル人への手紙9:28)
この聖句によれば、人間はまるで死ぬために生まれてきたかのようです。とすれば、この世の生は死と切り離しては考えられず、しかも、死後にさばきがあるとの告知は、まさに死の厳粛さを物語るものでもあります。
それにもかかわらず、多くの人は、生については真剣に考えるのに、死については深く考えることをしません。たとい死について考える場合にも、それは生の終局にどう対処するかについてであって、死そのものからは、目をそらして直視しようとはしないのです。むしろ、極力避けようとしがちです。そんなわけで、人間の死後について真剣にこれを究めようとする人は、ほとんどみられないのが実情です。
しかし、生が死の定めにある以上、われわれが生を考える場合、まずもって、この死を前提とするのでなければ、それはほんとうの意味で生を考えることにならないのではないでしょうか。
いったい、死とは何でしょうか。それは神から与えられていた命が、終わりを迎えることです。すなわち、命は神から与えられたものですが、人間が神から離反することによって、命の源とのつながりが切れてしまっているのです。その結果、せっかく神から与えられたいのちがしだいに枯渇し、やがて消え失せることになるのです。
では、人間は死んだ後どうなるのでしょうか。その答えいかんが、われわれの生の意味と価値を決定づけることになるわけです。したがって、これは人生最大の問題といってもよいでありましょう。
死後の人生の有無
「人がもし死ねば、また生きるでしょうか」(ヨブ記14:14)
これは、ヨブという人の口から発せられた問いです。この世において富裕であったヨブは、突如襲った不幸とわざわいによって、所有物のすべてを失いました。それだけではなく、10人の子らと死別し、しかも最愛の妻には去られ、その上自分の健康さえも損なわれて、地上に何一つ望みのもてない状態となりました。その結果、彼の関心はいきおい死後に向けられたのでした。彼は何もかも失い、裸同然となったこの世に、人間としてなおも生きつづける意味があるのかどうか、それはすべて、死後にも人生があるのかどうかにかかっていたといえます。
しかしこれは、ひとりヨブにかぎりません。人間ならだれしも、死んだらどうなるのか、それについて知りたいと思うのは、正直な気持ちにちがいありません。ですから、彼の問いは、古今東西を通じての人類共通の疑問でもあったわけです。
ところで、この疑問については、これまでも多くの人々によって、思索と探求がおこなわれ、いろいろな説が世に提供されてきました。代表的なものとして次のようなものがあります。
1、人間は死によっていっさい無に帰する
しかし、われわれはこの考え方にはとうてい同意できません。それには幾つかの理由があります。
A、人間がもし、初めから死ぬべきものとして造られていたのであれば、死は自然現象であるわけですから、だれもこれを悲しんだり嘆いたりするはずはありません。けれども、人間は死を恐れ、また嘆き悲しみます。これは人間にとって、死は自然ではない何よりの証拠です。
ですから、死は人間の定めであり、死によっていっさい無になるという考え方は、もともと人間の本性に反するものといわねばならないでしょう。
B、その証拠に、人間は死者をほったらかしにはしません。かならず丁重に葬って弔います。もし人間が死によっていっさい無になるのであれば、そんなことをするはずはありませんし、事実その必要もないはずです。しかし多くの人は、人が死んだらすべて終りで、あとは何も存在しないというふうにはとても考えられない。だからこそ、お墓にたいして異常なこだわりをもち、死者と別れを告げて後も、なんらかの形でなおも接触をつづけようとする。それが法事であったり、死者を迎えてのもてなしを意味するお盆であったりするわけでしょう。
もちろんそれは、生き残っている者の側の問題であって、死んだ者自身には直接関係のないことです。それは、情緒的人間の自然的発露ではあっても、霊の存在が客観的事実であることを示すものとは必ずしもいえません。
C、しかしながら、次に述べることについて、みなさんはどのようにお考えでしょうか。すなわち、われわれがこの世においてなした行為は、善に対して必ずしもそれに見合った報いがあるとは限りませんし、また悪に対して、それに相当する罰があるというわけでもありません。にもかかわらず、死んで一切が終りということになれば、善悪の清算や報いは、いつどこでどのようにして行われることになるのか。この疑問は、死後には何も存在しないという考え方に、どうしても納得できない決定的な理由といえます。
2、霊魂不滅説
人間は、他の動物と同じく肉体をもっています。が、それは存在のすべてではない。人間は単なる物質的存在にとどまらず、精神的・霊的存在(人格的存在)でもある。人間は道徳性をもっていますが、これは人格に関係する特性です。人間の本質的価値は肉体にではなく、この人格を形成する魂にあるはずです。
人間の肉体は物質ですから、年を取れば衰えて、枯れ木の朽ちるように消えていく。しかし、人間は人格的存在である以上、これは肉体の死とともに消えてなくなるとは考えられない。ということから、霊魂不滅という思想が生まれてきたわけです。肉体はなくなっても、肉体を脱ぎ捨てた霊魂はより自由な状態で霊の世界に移っていき、そこで永遠に生きつづけるにちがいないと考えるのです。
しかし、これにもいろいろな考え方があって、一様ではありません。たとえば、神道では、死者はこの地上にとどまっており、これまで住み慣れた家の裏山あたりに浮遊していると考えているようです。ですから、この霊をときおり生家に呼び戻して、生き残っている家族と一緒に食事をしてもらうということが、しきたりになっています。これを神道では神饌と言い、新嘗祭など皇室の伝統的行事にもなっています。
また仏教には、輪廻転生説という思想があります。仏教はほんらい無霊魂説なのですが、この思想はお釈迦さまが亡くなって後に、ヒンズー教から入り込んできた教えといわれています。
ですから、これはもともと仏教の思想ではないのですが、中国や日本においては、あたかも仏教本来の教えであるかのように説かれています。この説によれば、この世で良いことをした人は極楽浄土に行き、悪いことをした人は地獄に行くとされています。
生長の家という宗教などは、いろいろな宗教の教義を、あれもこれもと、みなかき集めて一つにしたような教えで、教派神道でありながら、死後についての教えは仏教の輪廻説に近く、それでいて死後の世界を七層界に分けたりもしています。
キリスト教においても、旧教のカトリックでは、死後の世界に天国と地獄があり、その中間に煉獄といわれるものがあると教えています。この世でいいことをした人は天国に入り、悪いことをした人は地獄に落とされる。しかし、天国に行けるほどよくはないが地獄に行くほど悪くもない、という人は煉獄に送られる。そこで罪滅ぼしがなされ、そこから天国に移される可能性も残されていると説きます。
しかし、こういう教えにはさまざまな矛盾があります。
A、まず一つには、死者の霊とされるものが(本当は死者ではなくサタンや悪霊なのですが)、本人が死んでからではなく、生きているうちにも現れることがあるとよくいわれます。これはどう考えたらよいのか、たいへん説明の困難な現象といわねばなりません。
B、さらに、われわれが救われて、さいわい天国に入れたとします。しかし、せっかく天国に救われても、もし地上に残している愛する家族が、毎日不幸や災いに遭って苦しんでいるとしたらどうでしょう。そのような有様を見て、どうして自分が救われたことを幸福と感じ、天国の生活を喜び楽しむことなどできるでしょうか。
C、それより何より、地獄に落ちた人々が燃える火の中で苦しみ続けるという。この世では苦しみから逃れるために自殺する人もいますが、来世では死にたいと思っても、霊魂不滅なら、死ぬこともできない。とすれば、地獄の火の中で、未来永劫に苦しみ続けるということになるわけでしょう。
しかし、いくら悪いことをしたからといって、神がそのような刑罰を是とし、このような状態を放置されるということが、果たしてあり得るものでしょうか。そんなことが、愛の神のみ旨であり定めであるなどとは到底思われません。
3、精神的な意味での永遠生命
これは先にあげた二つの考え方の折衷説ともいうべきものです。すなわち、霊魂不滅の思想をそのまま認めることはできない。かといって死後、なにもかもなくなってしまうというのでは、あまりにもさびしい。その空しさに耐えることはとてもできない、ということから次のように考えるのです。
A、たとえば、わたし自身は死んでなくなるとしても、なおこの世に生き残っている人々の心に、思い出として生き続けるはずである、というのです。
しかし、それは当然のことながら、生前交わりのあった人にかぎられます。それも年とともに、しだいに薄れていくことは避けられません。そのうえ、やがてその知人も亡くなったら、もはや他人の中の思い出というものは、そこで完全に消え去ってしまうことになります。
B、またある人は、次のように考えます。わたしの命は子に受け継がれ、さらに孫から曽孫へと子々孫々に継承されて、永遠に生き続けることになる、と。
これはこんにち、教育のある人たちの間に多く見られる考え方のようです。こうした考えは、いわば生物学的永遠生命とでもいいましょうか。一見、きわめて科学的現実的な考え方のようにみえます。たしかにわれわれの生命は子や孫に受け継がれていく。しかしながら、子や孫はいくら血のつながりがあるとはいえ、それはわたしとは別の人格です。いったい私自身の人格的生命はどうなるのか。これは、こうした考え方の中にその答えがあるようには到底思われません。
それだけではないのです。子供のある人はいいとして、子供のない人はどうなるのか。これについての答えは、このなかに何もありはしません。ですから、この考え方というのは、単なる詭弁にすぎず、自己欺瞞的な独りよがり、というほかないように思います。
以上、人間が死後どうなるのかについては、種々様々な考え方があり、いったい自分はどれをとればよいのか、ただただ迷うばかりというのが正直なところでしょう。
だいたい人間は、生まれる以前のことは何も知らないように、死んでから後のことも何もわからないのは当然です。なぜなら、生きているあいだは死を経験できませんし、死んだ後はこの世と絶縁状態になってしまうからです。ですから、人間は死について何も知ることはできず、したがってまた、これを語る資格もないわけです。
とはいえ、人間の生が死に向かう生であり、その生は死によって終りを告げるものである以上、われわれは、その死と、死んでからのことについて、何も知らないままで生きてゆくというわけにはまいりません。
4、復活による永遠生命
もう一つあります。それは聖書の告げるもので、復活の生命といわれるものです。聖書は、われわれが死について正しい知識をえるための確かな方法を教えてくれます。それはどんな方法でしょうか。
詩篇103:14には、次のように記されています。
主はわれらの造られたさまを知り、
われらのちりであることを
おぼえておられるからである。
人間を造ったのは神なのですから、人間が死んだらどうなるかは、神がよくご存じのはずです。われわれは、自分が生まれてくるとき、どんなふうにして生まれてきたのか、ほとんど何も知りません。しかし、母親は何もかもよく知っています。それと同じように、人間が最初造られたときの状態については、われわれ自身はなにもわかりませんが、造り主なる神はすべてをご存知のはずです。とすれば、死後どうなるのかについても、神はすべてを熟知しておられるにちがいありません。
ではその神は、人間の死後についてどのように言っておられるのでしょうか。世のほとんどの宗教は、死者の霊を認めていますが、神の言葉である聖書は、霊魂の不滅を認めてはいません。
これについて幾つかの聖句をあげてみましょう。
「生きている者は死ぬべき事を知っている。しかし死者は何事をも知らない。…彼らはもはや日の下に行われるすべての事に、永久にかかわることがない。…すべてあなたの手のなしうる事は、力をつくしてなせ。あなたの行く陰府には、わざも、計略も、知識も、知恵もないからである」(伝道の書9:5、6、10 参照引用句詩篇6:5、30:9、146:4)
「ちりは、もとのように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。伝道者は言う、『空の空、いっさいは空である』と」(伝道の書12:7)
この聖句はちょっと見ると、人間が死ぬと霊は肉体から脱けだして天に昇っていくかのように取れるかも知れませんが、これは決してそういう意味ではありません。同じ伝道の書のほかのところにはこうあるからです。
「人の子らに臨むところは獣にも臨むからである。すなわち一様に彼らに臨み、これの死ぬように、彼も死ぬのである。彼らはみな同様の息をもっている。人は獣にまさるところがない。すべてのものは空だからである。みな一つ所に行く。皆ちりから出て、皆ちりに帰る。だれが知るか、人の子らの霊は上にのぼり、獣の霊は地にくだるかを」(伝道の書3:19-21)
このように、聖書によれば、人間が死ぬと意識を持ったなにかが存続するというわけではない。むしろ意識は消滅してしまう。したがって、霊魂など存在するわけはない、ということなのです。
しかし、聖書のこの教えに、すぐには納得がいかないというかたがほとんどではないかと思います。無理もありません。それはわれわれが、幼児のころから、霊魂を不滅とする思想や、それを象徴する習俗的慣行などにかこまれて育ってきており、幼いときからそうした観念を植えつけられてしまっているからです。
死後の状態についての論証
人間が死んだ後どうなるかについて、これを確実に知るための方法は、人間が最初どのように造られたのかを明らかにすることです。それがわかれば、死後についても、自然と答えが出てくるはずです。
いったい人間は最初造られるとき、どんな方法また順序で造られたのでしょうか。聖書にはこのように記されています。
「主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった」(創世記2:7)
これによれば、人間は最初、土のちりで造られたというのです。土のちりは、現代の言葉でいえば物質を構成する元素ということになりましょう。これを素材にして人間が造られたというのです。それはきっと五体均整のとれた美しい容姿であったに違いありません。とはいえ、どんなに見事で美しくても、それは単なる物質でしかなく、せいぜい人形にすぎません。
しかし、これに神が命の息を鼻から吹き入れられた、とある。これは呼吸を開始したということです。その結果、人間は生きたものとなったというのです。言い換えれば、物を考えたり、話をしたり、動いて活動したりする、生きた存在となったということです。
そうすると、人間が死ぬとどうなるのか、答えは明白です。命の息が鼻から出ていって戻らなくなることです。その結果、物を考えたり、話をしたり、活動したりということは完全に停止し、魂は消滅します。そのあとには肉体だけが亡骸として残りますが、しかも、これは単なる人形であって物体にすぎませんから、いずれは腐って分解し、物質を構成する元素に還元することになりましょう。死とは、それだけのことであって、心とか霊魂といったものが存続するという可能性は何もないわけです。
この理屈は、いたって簡単明瞭であって、何もむずかしいことはない。とはいえ、日本人の多くは、この説明を聞いても、簡単に「そうかわかった」ということにはならないかもしれません。なぜならそれは、死者の霊は存在するものという潜入観念が、人々の頭の中にこびりついているからです。
そこで、この死についてのことわりを、どなたにも正しく理解していただけるよう、これからたとえを用いて説明してみたいと思います。そうすれば聖書の言っていることが、もっとはっきりするはずです。
では、いまここで、肉体を電球にたとえて考えてみることにしましょう。そして命の息を電流にたとえることにします。さらに心や精神また魂と呼ばれるもの、すなわち意識の活動を、熱や光にたとえて考えてみようと思います。
人間が生きた者となる経緯、また過程はどのようなものかというと、それをたとえで説明すれば、次のようになります。
ここに電球(肉体)があります。これに電流(命の息)が流れ込んできます。そうすると、電球は光を放射し、熱を発散(魂また意識の活動)するようになります。
では、人間が死ぬとどうなるのか。これは逆のことを考えればいいわけです。すなわち、それは電球(肉体)から電流(命の息)が出ていくことです。そうすると、光と熱(魂・意識)は消えてなくなります。それだけのことなのです。
このばあい、電球には光も熱もありません。電流も同様光も熱もないのです。ところが、光のない電球に、光のない電流が流れ込んでくると、光を発します。反対に電球から電流が出ていくとどうなるかといえば、光が消え、熱もなくなります。人体も、それとまったく同じなのです。
聖書の霊という語は、ヘブル語で「ルーアハ」といい、ギリシャ語で「プニウマ」と言いますが、いずれも風また息を意味し、意識をもった霊魂という意味はありません。
ところで、意識のない肉体に、意識のない命の息が吹き込まれると、そこに意識が生じ活動を開始します。この意識の活動を魂と呼ぶのです。
では、死ぬとどうなるかといえば、命の息が肉体から出ていって戻らなくなります。そうすると意識の働きは停止し、魂は消滅することになるわけです。その結果肉体は灰(土のちり)となりますが、そのあとに意識や魂だけが残り、肉体から遊離して存在を続ける、ということはありえないことなのです。
死は眠りである
ところで聖書は、死を眠りにたとえています。
「わたしは死の眠りに陥り」(詩篇13:3)
わたしたちは眠るとどうなるでしょう。まずもって無意識の状態になります。ですから、泥棒が入ってきてお金を盗っていっても気がつかないでいます。意識活動が停止しているからです。このように、死が眠りにたとえられているのは、死んだら意識がなくなるということを、それは意味しています。いいかえれば、これは意識をもった霊魂などというものは存在しない、ということの何よりの証拠となります。
われわれは、気絶や仮死状態から蘇生した人の話を、よく耳にすることがあります。ところが、こうした人々は意識が回復したとき、死んでいた間のことは何も知らず覚えていないのです。
実は、このわたしも少年のころ、落馬して気絶していたことがあります。そのあいだはまったく無意識で、なんの記憶もありませんでした。わたしは自分のこの経験からも、死後の意識をもった霊魂の存在は、事実ではないと、確信をもって言うことができます。
もちろん最近は、臨死体験の記録や報告が、広く流布されています。が、これは心霊現象にかかわる事柄であって、大変まぎらわしく、やっかいな問題でもありますので、これについての詳細は、別の機会に取り扱うことにしたいと思います。
それにしても、こんにち霊魂不滅の思想は、テレビなどの影響もあり、世界中に広く知れわたっています。が、もちろんこれは事実であるからではありません。それよりはむしろ、人間自身、死をもっていっさい無になると考えることにはたえられないところから想定された、いわばこれは来世にたいする強いあこがれや願望の表現にすぎず、それを物語るものというべきでしょう。
もちろん聖書の中に、霊魂不滅ととられやすい記事があるのは事実です。だからこそ教会によっては、霊魂の存在を、あたかも聖書の教えであるかのように説いてきたところもあるわけです。しかし、霊魂不滅というのは、もともとギリシャ思想であって、実は聖書の教えではないのです。
それにもかかわらず、キリスト教会はこれまで、なぜかこれに触れることを故意に避けてきた感がありました。それだけに、昔から、死は眠りであり、死者の霊は存在しないということを、教理の一つとして明確に説いてきたわが教団は、他教派から非難されたり冷笑されたりしてきたほどです。
しかし、戦後になって世界的に著名な神学者オスカー・クルマン博士の著書『霊魂の不滅か死者の復活か』と題する本が翻訳出版されましたが、この本によって博士は、キリスト教会の霊魂不滅の思想は、ギリシャ思想の影響によるものであって、聖書の釈義上からは絶対に出てこない考え方である、と断言しています。
そういうわけで、この本が出てからというもの、わたしどもの教会がこれまで説いてきた「死は眠り」という教えに対する他教派からの非難は、これによってぴたりと、なりをひそめてしまったという経緯があります。
では、死によって一切無に帰するのか?人生はやはりこの世かぎりなのか?もしそうだとすると、ここに一つの大きな疑問が生じます。それは、人間が死によって本当に永遠に無になってしまうのか、ということです。もしそうなら、聖書の次の言葉「『わたしたちは飲み食いしようではないか。あすもわからぬいのちなのだ』」(コリント第一の手紙15:32)という生き方になってしまっても仕方がない、ということになりはしないでしょうか。
そうなると、聖書のいう救いはそもそも何を意味するのか。われわれの救いは、いったいどういうことになるのか、ということです。
眠った者はいつかまた目を覚ます
死が眠りにたとえられているのは、死者には意識がないからなのですが、しかしそれは、永遠の滅びや絶対の無に帰することではありません。なぜなら眠りは、そのあいだ意識が働かなくなるとはいえ、眠りは眠りであって死滅ではありません。いつか目覚めるときがくるはずです。それが聖書のいう復活という出来事なのです。すなわち、死んでいる間は意識がないとしても、その状態が永遠につづくのではありません。そうではなく、死者にはやがて、復活による永遠の夜明けがやってくるのです。これが聖書に約束されている新天新地の出現です。そのとき、復活により目覚めて意識を回復した者は、そこに迎え入れられて、その後は永遠に生きるものとなるのです。
この復活については、聖書に多くの言及があります。
「このことを驚くには及ばない。墓の中にいる者たちがみな神の声を聞き、善をおこなった人々は、生命を受けるためによみがえり、悪をおこなった人々は、さばきを受けるためによみがえって、それぞれ出てくる時が来るであろう」(ヨハネによる福音書5:28、29)
「わたしをつかわされたかたのみこころは、わたしに与えて下さった者を、わたしがひとりも失わずに、終りの日によみがえらせることである。わたしの父のみこころは、子を見て信じる者が、ことごとく永遠の命を得ることなのである。そして、わたしはその人々を終りの日によみがえさせるであろう」(ヨハネによる福音書6:39、40)
これは何からの引用かわかりませんが、聖書にはこんな言葉もあります。
「『眠っている者よ、起きなさい。死人のなかから、立ち上がりなさい。』」(エペソ人への手紙5:14)
しかもイエスは、このことの確かな保証として、実際に死人をよみがえらせるという奇跡をおこなっておられます。ヨハネによる福音書11章に、次のようなことが記されています。
イエスが伝道旅行で遠出をしておられたとき、ベタニヤから使いがきて、愛する弟子ラザロが死んだという知らせをうけました。そのときイエスは、弟子たちに向かって「ラザロは眠っている。わたしは彼を起こしにいく」といわれました。でしたちが「眠っているのなら、ひとりで起きるでしょう」というと、イエスはあらためて「いやラザロは死んだのだ」といわれたのです。そして、ただちにベタニヤに戻り、墓の前に立って「ラザロよ、出てきなさい」と大声で呼ばわると、死んですでに四日もたっていたラザロが、生き返って墓の中から出てきた、とあります。
これは、イエスが先に、「世の終わりに死人をよみがえらせる」と宣言された、それを確証する目的でおこなわれた奇跡であったのです。しかも、イエスご自身、やがて十字架の死後三日目に復活されましたが、これはわれわれのさきがけとしてのそれであり、同時にこのラザロの復活は、イエスの復活の前触れとしての意味をもつものでもあったのです。
この死後の復活というのは、聖書独自の教えであり、これは人間の死後に関する最も確かで、しかも慰めと希望に満ちた輝かしい教えです。世界に数多くの宗教があり、それぞれ死後について、さまざまな教えを説いてはいますが、聖書のこの復活の教えに勝るものはほかにないといってよいでしょう。
しかし、なかにはこういう人もいます。復活が事実なら、それは確かにすばらしい教えにはちがいないが、死は眠りとしても、では、よみがえりのときまで遺体はどうなるのか。ある者は何十年何百年いや何千年もの間、暗い冷たい墓の中で過ごすのか、そんなことは、考えただけでもゾッとするし、うんざりだ。そんなことは考えたくもないし、信じる気にはとてもなれない、というのです。
けれどもこれは大変な誤解といわねばなりません。なぜなら、遺体といってもそれは骨か灰、意識のない単なる物質の塊にすぎません。もはや本人とは無関係の存在物にすぎないのです。
それよりなにより、死んだ者はもう意識がないのですから、本人にとって時間は存在しないも同然です。したがって、たとい、遺骨が墓の中ですごす時間が百年千年であっても、それは生き残っている人にとってのことにすぎず、死者自身にとっては、時間は存在しないのですから、ほんの一瞬のことにすぎません。ですから当人としては、目を落とす次の瞬間には目を覚まして、再臨のキリストに迎えられることになるわけです。
「またわたしは、天からの声がこう言うのを聞いた、『書きしるせ[今から後、主にあって死ぬ死人はさいわいである]』。御霊も言う、『しかり、彼らはその労苦を解かれて休み、そのわざは彼らについていく』」(ヨハネの黙示録14:13)
ここに、「その労苦を解かれて休み」とあります。死は眠りであり無意識であるからこそ、それは「労苦からの解放」になるわけです。しかも眠りである以上、いつか目覚めるときがくるはずです。ですから、死者はよみがえりの朝を待ち望みつつ、しばらくの休息にはいることになるのです。「死がさいわいである」といわれているのは、まさにそのためなのです。
神のうちに隠されている命
われわれは死んだのちどうなるのか、この問いにたいする聖書の回答は、「死は眠りである」ということですが、これには二つの意味があります。
ひとつは無意識状態ということで、これはとりもなおさず、意識を持った霊魂は存在しないということです。すなわち、霊魂不滅の否定です。
もうひとつは、死が眠りである以上、いつか目を覚ます時がくるということです。すなわち復活です。
では、死んでから復活するまでの間は、どこでどのような状態ですごすのか。もし墓の中で、ということであるとすると、さびしいやら、気味わるいやらで、それはとてもやすらぎの状態とは思えないという人もあろうかと思います。この疑念にたいしては、二つの面からの説明が必要かもしれません。
ひとつは、まえにも触れたように、死体は墓の中に入れられるとはいえ、それは骨また灰であって、単なる物質にすぎず、本人とは無関係といえなくもありません。のみならず、死者は無意識である以上、死者にとっては、時間も存在しないのですから、死んでから復活するまで、たとい百年経とうが千年経とうが、本人にとっては一瞬にすぎない。目を落とす次の瞬間には目を覚まして、再臨のキリストにお会いすることになるわけです。
以上の説明によって、死後についての疑念は一応解消されるはずではないかと思います。
しかし、それにしても、いったい死によってわたしという存在はどうなるのか、やはり、まったくの「無」ということには、どうしても納得がいかないという方もおられましょう。
この疑念にたいして、聖書になにか解決の手がかりとなるものがないのかどうかですが、次の聖句がその答えになるのではないかと思われます。
「このように、あなたがたはキリストと共によみがえらされたのだから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右に座しておられるのである。あなたがたは上にあるものを思うべきであって、地上のものに心を引かれてはならない。あなたがたはすでに死んだものであって、あなたがたのいのちは、キリストと共に神のうちに隠されているのである。わたしたちのいのちなるキリストが現れる時には、あなたがたも、キリストと共に栄光のうちに現れるであろう」(コロサイ人への手紙3:1-4)
ここに、われわれの命は、神のうちに隠されているとあります。地上においては、肉体は墓の中かもしれませんが、天においては、われわれのいのちは神のうちに隠されているという。なんという慰めにみちたありがたい神のおはからいでしょうか。
ただし、この命は意識をもった霊魂ではないことに注意する必要があります。繰り返しになりますが、聖書のいう命は息のことであって霊魂を意味しません。すなわち、人間が最初神によって造られたとき、神はまず人間の体を造り、それに命の息を吹き入れられた。そのとき、人間は生きた者となったとあります。この場合、肉体には意識がなく、命の息にも意識はありません。意識のない肉体に意識のない息が吹き込まれたとき、人間は生きた者となったという。すなわち、意識を持つ存在となり、霊魂としての活動が始まったというのです。では、死ぬとどうなるのでしょう。
「ちり(肉体)は、もとのように土に帰り、霊(息)はこれを授けた神に帰る」(伝道の書12:7)
肉体から命の息が出て行けば、魂すなわち意識活動は停止し、消滅することになるのです。
そこで問題は、命です。これはたんなる息であって、意識をもった霊魂では決してないのです。しかし、神のうちに隠されているという、その命がはたして息だけなのか、という疑問をいだかれるかたもおられましょう。これが、肉体でもなければ、意識をもった霊魂でもないとすると、この命の息とはそもそも何なのか。これについて、聖書にはあまり明確な説明はありませんが、これは仏教で言う「業」(カルマ)に当たるものと考えれば、とてもわかりやすいのではないかと思います。
仏教の言う「業」とはなにか。これは、その人の生前になしたわざ、すなわち言葉なり行為なりをさします。仏教では、この業が輪廻するというのですが、その場合、輪廻の主体はなにかといえば、それは「我」ではなく「業」それ自体であるというのです。なぜなら、仏教は霊魂の不滅を認めていないからです。では業の報いはだれが受けるのか、これについての明確な答えはないようです。ここに仏教の根本的な矛盾と問題点があるのですが、これに対する納得のいく説明は、仏教にはなく、むしろキリスト教の復活の教義にこそ、それについての真の答えがあるということになろうと思います。
それはともかくとして、神のうちに隠されている命、これは意識をもった霊魂ではもちろんないのですが、仏教の言う「業」にあたるもの、すなわち生前の言葉や行い、品性、人格、とくに信仰、愛、霊性、そういったものを内包する命、ということになりましょう。その意味では、個性を備えた命、すなわち、「わたし」という個的人格そのものといってもよいでしょう。これは、死によってなくなるわけでもなければ、神に忘れられるということは決してないということなのです。
しかもこの命が、神のうちに隠されるのは、その人が肉体的に死ぬときではなく、キリストを信じたとき、そのとき十字架上で死なれたキリストと共に、生まれながらの「古き我」に死ぬことになる。それと同時に、復活されたキリストの新しい命に生きる者となる。その霊的命が、肉体が死んでいるあいだも、神のうちに隠され、守られているということになるのです。しかし、これはどこまでも意識をもった霊魂とは異なるものであることを明確に認識することが必要です。
とはいえ、神のうちに隠されているこの命がどのようなものかは、あまり定かではありません。それは神のうちに隠されているものである以上、人間が明確にこれを知り得ないのは当然でしょう。しかし、わたしがとくに、ここで申し上げたいのは、人間は死後決して冷たい墓石の下で過ごすというわけではないということです。それどころか、このあいだはむしろ、母親の腕に抱かれる赤ん坊のように、神のみ懐に抱かれて眠っている状態を思い描いてみてはどうでしょうか。その赤ん坊が目を覚ますとき、それが復活なのです。
いずれにせよ、われわれの命が、神のうちに隠されているということは、それがやがてまた現れ出るときがくるということを意味することにもなるのです。それはいつかといえば、言うまでもなくキリストの再臨のとき、ということになります。使徒ヨハネはこういっています。
「わたしたちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜わったことか、よく考えてみなさい。わたしたちは、すでに神の子なのである。世がわたしたちを知らないのは、父を知らなかったからである。愛する者たちよ。わたしたちは今や神の子である。しかし、わたしたちがどうなるのか、まだ明らかではない。彼が現れる時、わたしたちは、自分たちが彼に似るものとなることを知っている。そのまことの御姿を見るからである」(ヨハネの第一の手紙3:1、2)
ここに述べられていることは、われわれの死後の命についても、同じように言えることだと思います。その命が、個性や人格、信仰や徳性を内包するとはいえ、それが意識をもった霊魂ではないとすると、いったいそれはどのようなものなのか。突飛なたとえですが、意識のない命、それは冬眠状態と考えてみてはどうでしょうか。あるいはまた、イメージがあまりよくありませんが、命の冷凍状態と考えてみるのも、理解の助けになるかもしれません。
ただしそれは、霊魂の機能の停止、また活動の休止状態を説明するための譬えにすぎず、それはどこまでも理解を助けるための方便として申し上げたまでのことであって、死んだら本当に冷凍になるなどとは考えないでください。
死んでいるあいだのことは、さきにも述べましたように、やはり神のあたたかいみ懐にいだかれて眠っている状態と考えるほうが適切であり、より真実に近い状態といってよいのではないかと思います。
いずれにしても、死後は意識がない。だが、やがて目覚めるときがくる。これが復活・再生です。そのとき、死者は肉体の再生と同時に意識も回復し、魂が再び活動を開始するのです。そしてそれは、これまでのような不自由な肉の体ではなく、天使と同様、時間と空間の制約をうけない自由な霊の体にかえられるのです。
こうして人間は、この地上とは異なる新しい世界で、この世の生活とは比較にならない、まったく想像を絶する、新しい永遠の生活がはじまることになるのです。
「霊魂不滅説」はサタンの欺瞞思想
それにしても、こんにち多くの人にとって、せめてもの希望となっている霊魂不滅の思想を、聖書がこんなにも強く否定するのはなぜなのか、ということです。それは、サタンの編み出した偽りの思想であるからです。
創世記に記されているエデンの園の物語によると、神はエデンに善悪を知る木を生えさせ、アダムとエバにこれを食べることを禁じ、これを食べるときっと死ぬ、と警告されました。ところが、誘惑者サタンは二人に対して、これを食べても決して死ぬことはない。それどころか、むしろ神のように賢くなる、とささやいたのです。すなわちサタンは、霊魂不滅の思想によって、アダムとエバを欺くことにみごとに成功した。これに味を占めたサタンは、このときから、いつも同じ手口で人類を欺きつづけているのです。
これがおそるべき欺瞞思想であるのは、つぎの点によってもあきらかです。
1、これは宗教家を堕落させるまちがった思想である
たとえば、かつて旧教のカトリック教会は、寺院建造の資金を得るために、免罪符というものを作り出しました。これを高いお金で買うなら、地獄に落ちている家族の罪滅ぼしになって、彼らを天国に救うことができると説いたのですが、これは霊魂不滅の思想を前提とする欺瞞的教義なのです。
わが日本においても、仏教のお坊さん方にとっては死者の弔いや供養が仕事のすべてとなっており、そのため、墓地経営がいまやお寺の本業となっています。死者はいわば、お金儲けの手段にされているありさまです。
こうして、寺院にとって生きている人々は布教や救済の対象ではなくなってしまっている。これはあきらかに宗教家の堕落といわねばなりません。それも、もとはといえば霊魂不滅という、サタンの発明になる欺瞞的教義が、その誘因また発端となっています。こうした宗教、また宗教家の堕落は、まさにその必然的所産にほかならないのです。
2、これはキリスト再臨の教義をなおざりにさせる危険な思想である
もし霊魂が不滅であり、人間は死後ただちに天国や地獄に行くのなら、キリスト再臨の必要はなくなってしまいます。そのためかどうか、霊魂不滅を信じているクリスチャンの多くは、聖書に明白なキリスト再臨についての教えには、ほとんど注意を払わず、無関心の傾向がみられます。
たとい、これを否定はしないまでも、真剣に信じて待望するという姿勢が見受けられません。これはあきらかに、サタンの欺瞞思想に籠絡されている何よりの証拠というべきでしょう。
3、これは人々に救いの準備を怠らせる危険な思想である
もし死者に意識がないのなら、死んでから救いの準備をするというわけにはまいりません。それは生きている間になされなければならないはずです。なぜなら、聖書は次のように言っているからです。
「死においては、あなたを覚えるものはなく、陰府においては、だれがあなたをほめたたえることができましょうか」(詩篇6:5)
「陰府は、あなたに感謝することはできない。死はあなたをさんびすることはできない。墓にくだる者は、あなたのまことを望むことはできない」(イザヤ書38:18)
これによれば、死んだ者は神を信じることも悔い改めることも祈ることもできないというのです。そうだとすると、目を落とす次の瞬間には、その人の運命が永遠に決定することになるわけです。
それにもかかわらず、霊魂が不滅であるということになれば、救いの備えは死んでからでもできるということになる。そうであれば、あえて生きている間に神を信じ、また救いのために備えねばならない理由も根拠もなくなります。
こうして、人々は救いの備えをおろそかにしているあいだに、突如として死が訪れた場合、その人から救いの機会が永久に失われてしまうことになりかねません。
とすれば、こんな恐ろしい危険な思想がほかにあるでしょうか。
霊魂不滅の思想は、エデンの園でサタンがアダムとエバを神から引き離すために用いた欺瞞なのです。
人間の死後についての極端な考え方
人間の死後の状態については、二つの極端な誤った考え方があります。
1、一つは、人間が死んだら一切は無また空であり、来世などは存在しないという説です。
もしそうであるのなら、人生には前途になんの希望も慰めもないということになってしまいます。
2、他の一つは、人間は死によって肉体はなくなっても、魂は不滅であるという思想です。
これは、聖書に根拠がないばかりか、聖書の教えとあきらかに矛盾します。その結果、神の言葉である聖書の教えを真っ向から否定することにもなってしまいます。
以上は、人間の死後に関する両極端のあやまった考え方です。これらはいずれも聖書の教えに基づくものではなく、サタンから出ている偽りの思想です。人間の死後の状態についてのもっとも健全な教えは、人間のたんなる憧憬や願望からうまれた思考や所論ではなく、神の啓示に基づくものでなければなりません。いずれにしても、人間の死後についての正しい知識また理解は、神の言葉である聖書の教えによるほかはないことを確認し、このことを深く心に銘記する必要があります。
繰り返しになりますが、巷間に深く根を張っている霊魂不滅の考え方は、もともとギリシャの哲学思想であって、それはいわば観念論にすぎず、客観的事実であるという何の根拠もありはしません。
事実は、神の啓示である聖書が言うように、人間が死んだらそれは眠りであって、意識を持った霊魂など存在しないのです。したがって、救いの準備は死んでからではもう遅い。それは生きている間になされなければならないという、これこそが真実で確かな教えであり、神からの厳粛な警告でもあるのです。
それにしても、死は眠りであるという。これは、なんと心安らぐメッセージであることでしょう。眠りは無意識なら、それは人生の「労苦からの解放」を意味する。しかも死は眠りである以上、いつか必ず目覚めるときがくる。それが聖書の言う復活なのです。そのときにわれわれは、名実共に永遠の命が与えられ、再臨の主キリストに伴われて、天の家郷に移り住むことになるのです。
人生の旅路に、労し、喘ぎ、疲れた者にとって、この希望と慰めにみちた輝かしい晨の待望、これにまさる幸いが、果たしてほかにあるでしょうか。
仏・キ両教の死後観の比較
仏教とキリスト教の死後観のむすびとして、この二つの教えの要点と結論を比較してみましょう。
仏教の死後観
仏教の死後観がすでに述べたようなものであるとすると、人間は死んだらすべておしまいで、そのあとなんにもなくなってしまうのでしょうか。
そうです。そのとおりなのです。とくに仏教の場合、死者の霊魂をみとめていないのですから、当然死後の世界もなければ、後生もないことになるわけです。死によって、一切は無になり、空に帰するのです。そのあとに、なにかが残るとすれば、それはただ、人格や霊魂から剥離し分断された業(カルマ)だけということになります。この業、すなわち非人格的な業だけが、未来永劫に輪廻し続けることになるわけでしょう。
少なくとも意識をもった魂というものは、死と同時に解体消散して、霧のように、空気のように、いや人間が存在に入る以前の状態に還元されることになるわけです。したがって、仏教の教えでは、一度眠りについたらそれっきり、未来永劫に目ざめるときはこない。一切皆空、涅槃寂静 、これはわかりやすくいえば、真空状態になるといってもよいのではないかと思います。
ですから、死後における慰めや希望がもしあるとすれば、いささか逆説的な言い方になりますが、それは、死それ自体ということかもしれません。というのは、不治の病にとりつかれた人、負いきれない悩みごとをかかえている人が、なんとか楽になりたいとしきりに願う、その場合残された道はただ一つ、みずからの生命を断つということでしょう。確かに、死はそのような人の願いをかなえてくれる唯一の方法であるにちがいありません。なぜなら、死こそが、仏教のいう救い、すなわち生の断滅による「苦」からの永遠の解放を可能にしてくれるものだからです。
キリスト教の死後観
これに対して、キリスト教の教えはどうなのかということですが、さきに述べましたように、死者の霊魂を認めないという点では、仏教とほとんど同じなのですから、その意味からすれば、人間が死んだ後どうなるかということも、一応仏教と同じ考え方といってよいことになります。
しかしそのことは、人間の死後には、もはや未来もなければ、なんの希望もないということではありません。それどころか、死後になお永遠の輝かしい希望が残されているのです。
といっても、仏教もキリスト教も、どちらも霊魂の不滅を認めないのだとしたら、どうして死後にも、未来や希望があるといえるのか、この点に矛盾を感じる方がおられるかもしれません。当然です。
実は、このあたりにこそ、仏教とキリスト教の根本的な相違点があるのです。そしてまた、これが両教の教えの大きな分かれ目ともなっているわけなのです。
すなわち、これまでみてきましたように、仏教の極楽浄土の教えも、輪廻転生の考え方も、さらには因縁因果の業報思想も、どれ一つとして、霊魂不滅を示すものではなく、またそれを立証するものでもありません。死は仏教の教えからすれば、無にほかならず空に等しいのです。
しかし、神を信じる者の世界においては、死はすべての終わりでもなければ、一切の無・空でもない。むしろ、死はまさに生命への門なのです。
なぜなら、神はキリストの十字架と、そのあがないを信じ受け入れるすべての人に、復活による永遠の生命を約束しておられるからです。
「わたしはよみがえりであり、命である。わたしを信じる者は、たとい死んでも生きる」(ヨハネによる福音書11:25)
人間の罪の結果である死は、キリストの十字架の死と復活によって滅ぼされたのです。この復活のキリストは、パトモス島に幽閉されていた弟子ヨハネにお現れになり、次のように仰せになっています。
「恐れるな。わたしは初めであり、終りであり、また、生きている者である。わたしは死んだことはあるが、見よ、世々限りなく生きている者である。そして死と黄泉とのかぎを持っている」(ヨハネの黙示録1:17、18)
このように、復活の主キリストは、いまや死と命のかぎを持っておられます。このキリストを信じる者は、やがての日、キリスト再臨のとき、死からよみがえらされることによって、死への勝利宣言を声高らかに叫ぶことになるのです。
「ここで、あなたがたに奥義を告げよう。わたしたちはすべて、眠り続けるのではない。終りのラッパの響きと共に、またたく間に、一瞬にして変えられる。というのは、ラッパが響いて、死人は朽ちない者によみがえらされ、わたしたちは変えられるのである。なぜなら、この朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。この朽ちるものが朽ちないものを着、この死ぬものが死なないものを着るとき、聖書に書いてある言葉が成就するのである。
『死は勝利にのまれてしまった。
死よ、おまえの勝利は、どこにあるのか。
死よ、おまえのとげは、どこにあるのか』
死のとげは罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべきことには、神はわたしたちの主イエス・キリストによって、わたしたちに勝利を賜ったのである。だから、愛する兄弟たちよ。堅く立って動かされず、いつも全力を注いで主のわざに励みなさい。主にあっては、あなたがたの労苦がむだになることはないと、あなたがたは知っているからである」(コリント人への第一の手紙15:51-58)
この聖書に約束されている輝かしい復活の希望について、矢内原忠雄氏(元東京大学総長)は次のように述べています。
「もし人間に希望というものがあるとするならば、イエスの復活にだけ我々は真の希望を見出すことができる。それ以外の望みや期待は希望の名に値せざる空しき楽観に過ぎないのである」。
「多くの人は希望なくこの世を去る。哲人は或は平静に世を去ることができるであろう。しかし希望と感謝と勝利感をもって死の川を渡る者は、復活の希望をもって天に凱旋する者だけであろう」。
要点の確認
- 死は万人共通の定めであり、だれひとりこれをさけることはできない。にもかかわらず死ぬときについて考える人はいても、われわれは死後どこへどうなるのかについて考える人はまれである。
- 世のほとんどの宗教は、霊魂不滅の思想を教えとしている。だが、神の言葉なる聖書は、これをサタンの作り出した欺瞞思想として、強く否定している。かつてサタンはエデンの園において、この霊魂不滅の思想を餌に、アダムとエバを神に背かせたが、かれは今日まで、同じ手口を用いておおくの人を欺きつづけてきた。いまもなお、世の大多数の人は、この欺瞞的教えの犠牲となっている。
- ところで、仏教とキリスト教の霊魂観は同じである。死後、意識を持った霊魂というものは存在しないという考え方で一致している。すなわち、仏教は、人間の死後は「一切皆空」と説く。これに対して、聖書の示す死後観はどのようなものか。聖書は、人間の肉体と霊魂とを別個のものとする二元論的な捉え方はしない。最初、人の肉体を造った神が、これに息を吹き入れられると、人間は生きた者となったという。言い換えれば意識の活動の開始である。この意識の機能また活動体が魂と呼ばれるものなのである。したがって、死は肉体から命の息(これに意識はない)が出て行くことであって、そのとき意識の活動は停止し、魂は消滅する。意識をもった不滅の霊魂など存在しない。これが聖書の霊魂観である。
- だが仏教とキリスト教は、霊魂観は同じでも死後観まで同じとはいえない。むしろ正反対である。仏教のいう死は、未来永劫の眠りであって再び目覚めることがない。いわば無また空の状態になるという。これに対して、キリスト教は、死は眠りであって、やがての日に再び目を覚ますときがくる。死はそれまでの安らかな休息であるというのである。すなわち、死者の霊魂は認めないが、死は眠りであるから、いつか目をさます時がくる。そのように、キリスト教は死者の復活と永遠の生命の回復があると説く。
- 聖書は死を、眠りという言葉で呼んでいるが、これには次の二つの側面的意味がある。ひとつは、死は眠りであって、それは無意識状態であることを意味する。したがって、霊魂不滅の思想は事実ではありえない、ということである。他の一つは、死は眠りであるから、それは永遠の死滅を意味しない。眠った者は、いずれ目を覚ますときがくる。それと同じように、死者はやがて復活し、永遠に生きる者となるということである。
- イエスは生前、世の終わりに死者をよみがえらせると宣言された。そしてさらに、死後四日もたっていたラザロを墓の中からよみがえらせることによって、その宣言の真実性を確証された。それとともに、ご自身十字架の死後、三日目に復活することによって、人間の罪がもたらした死を滅ぼされ、同時にそれによって、世の終わりにおけるわれらの復活の先駆けとなられた。
- こうして、人間の死はいまや、死ぬべき命が不死の命への移行を画する転換点としての意味をもつものとなったのである。故に聖書は「今から後、主にあって死ぬ死人はさいわいである」また「しかり、彼らはその労苦を解かれて休み、そのわざは彼らについていく」と告げている。死は労苦からの解放であり、休息であるという。したがって、人間の死後観について、これ以上の確かで、しかも希望と慰めに満ちた教えは、ほかには存在しない。